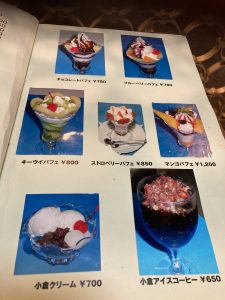こんにちは(^^)受付スタッフ福田です( ‘ ‘♬)
暖かくなってきたと思ったら、朝晩はまだ冷え込みますね(^^;
私はせっかくなおした毛布を1枚また引っ張り出して使っています(笑)
さて、先日たけのこ掘りに行きました( ¨̮ )
毎年恒例になりつつあり、院長家族とスタッフの何人かとで参加させて頂きました( ¨̮ )

昨年も参加しましたが、たけのこって以外に掘るのが難しいんですよ(^^;
土から出ているたけのこを見つけても掘り出すまでに労力を使います(笑)


なので、合間に現実逃避という名の休憩を、、、、(笑)
当日は暑かったのですが竹林がいい感じに日差しを遮ってくれていて涼しく過ごせました(^^♪

そして、たけのこを掘る瞬間は何度味わっても達成感でいっぱいになり、
とったどー!!って感じになります(≧▽≦)


来年も頑張りまーす(*’-‘*)ノ“