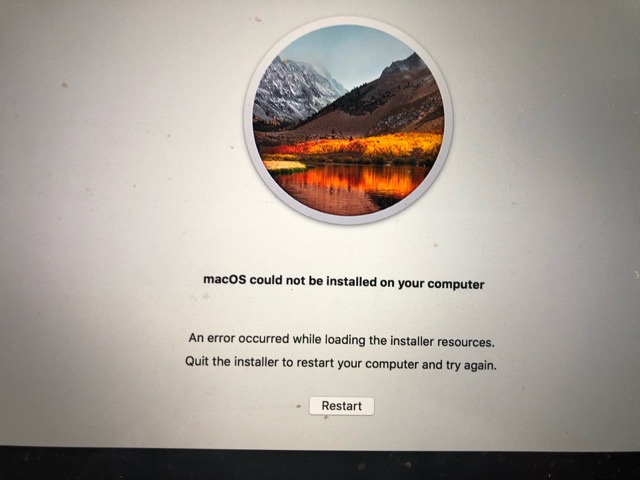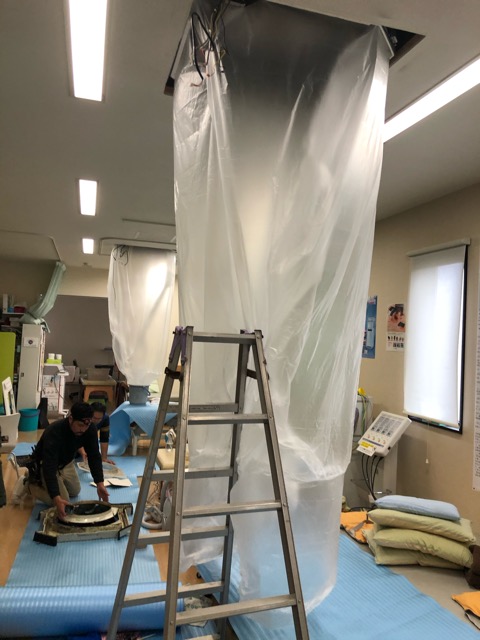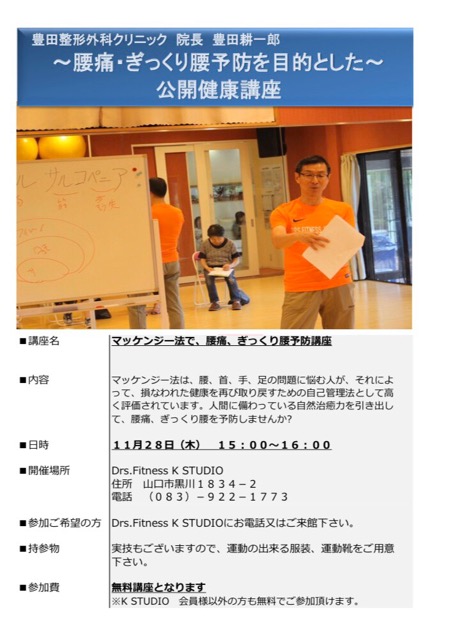新年明けましておめでとうございます
2020/01/11



新年明けましておめでとうございます。とよた整形外科クリニックは今年も地域医療に貢献できるようスタッフ一同頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。
さて私の年始は岐阜から始まりました。初日の出を拝んで気を引き締めた後、三重の伊勢神宮に初詣をしました。(お伊勢さん詣でですね)伊勢神宮は外宮から最初にお詣りして時間があったので内宮にも行きましたが内宮はさすがに人が多かったです。翌日おかげ横丁で伊勢名物赤福本店のおしるこを食べて帰りました。その後名古屋から帰りましたが気持ちも引き締まりました。