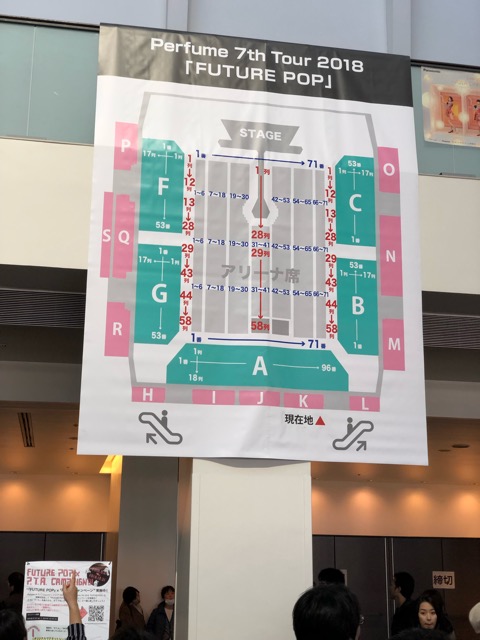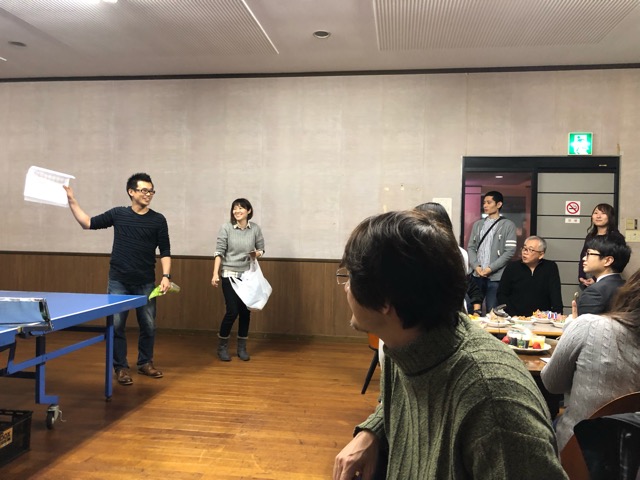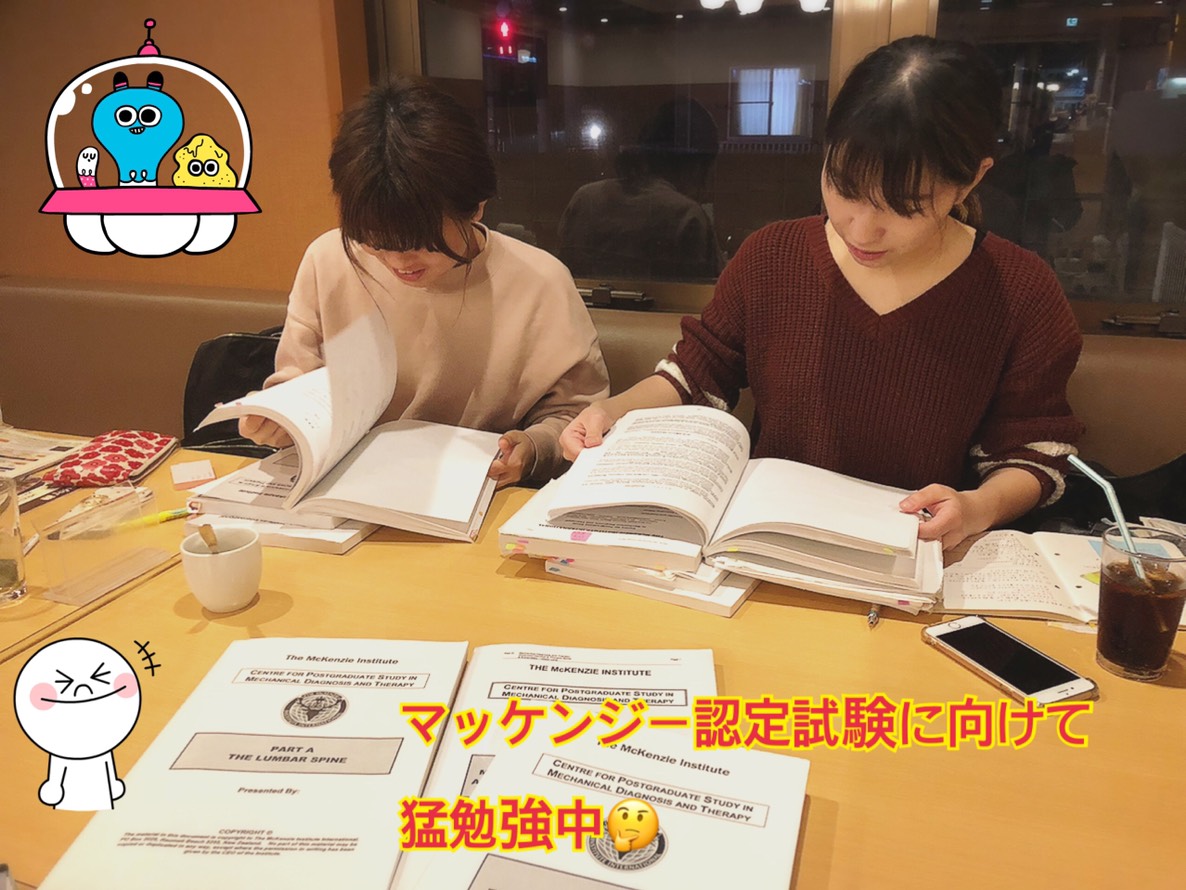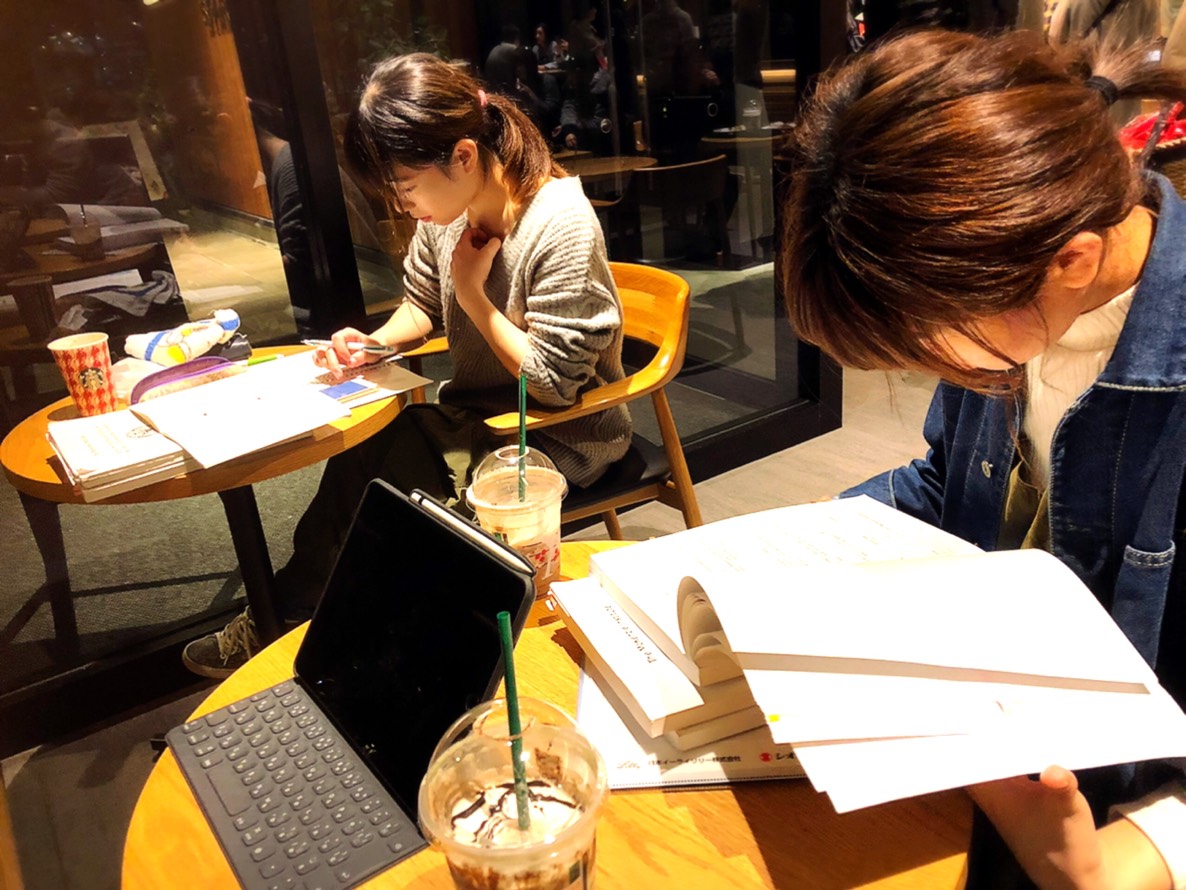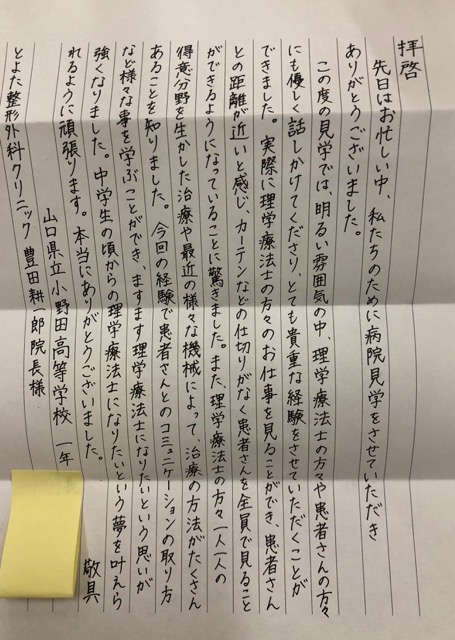こんにちは受付スタッフ福田です!!
ずいぶんと寒くなってきましたね(^^;
先日、友達をお家に招きゆずジャムを作りました(^^♪
お友達監修です(^^)





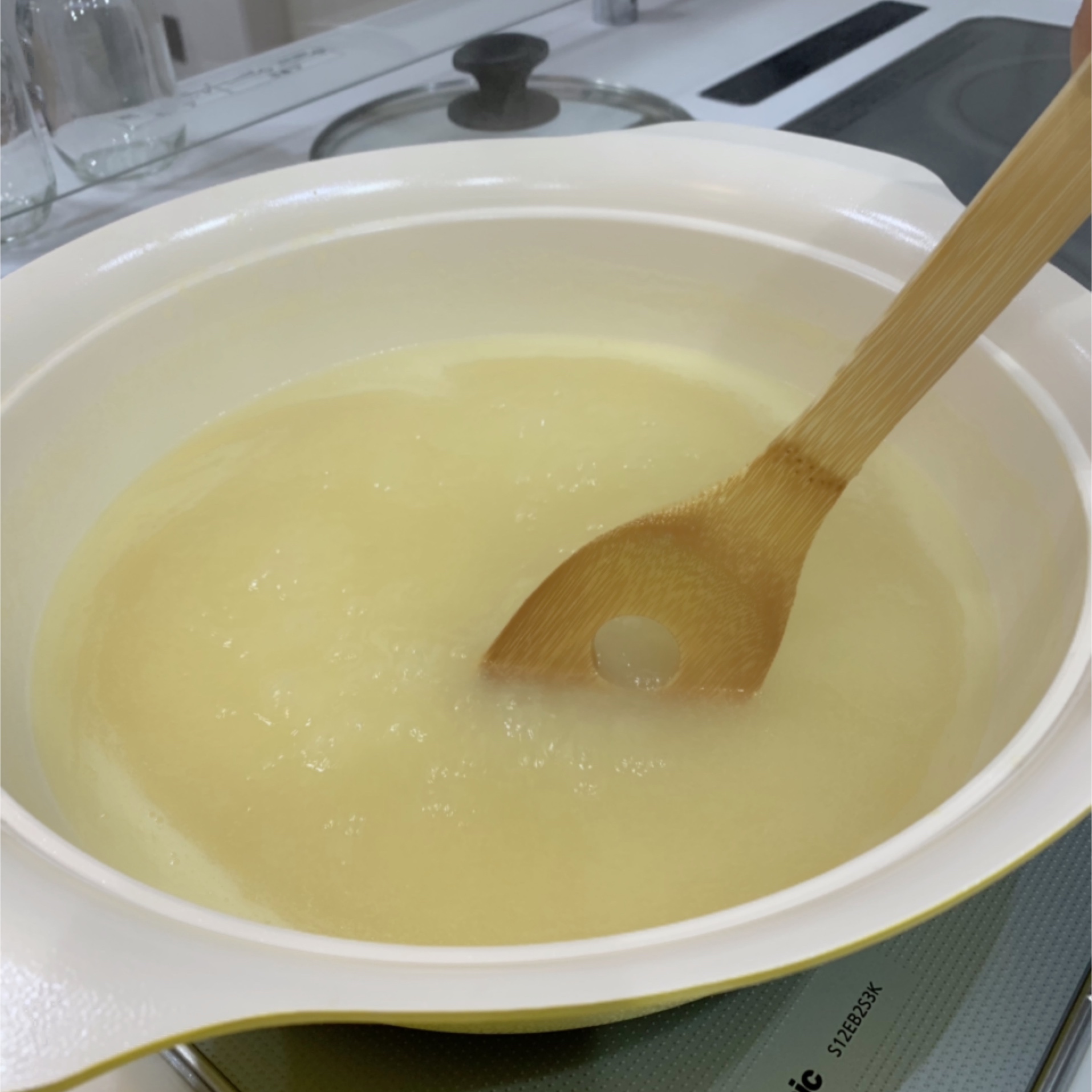



見た目通りに、とっても美味しいジャムが出来ました♡♡♡
また、来年も一緒に作りたいです(ˊᗜˋ)
ずいぶんと寒くなってきましたね(^^;
先日、友達をお家に招きゆずジャムを作りました(^^♪
お友達監修です(^^)





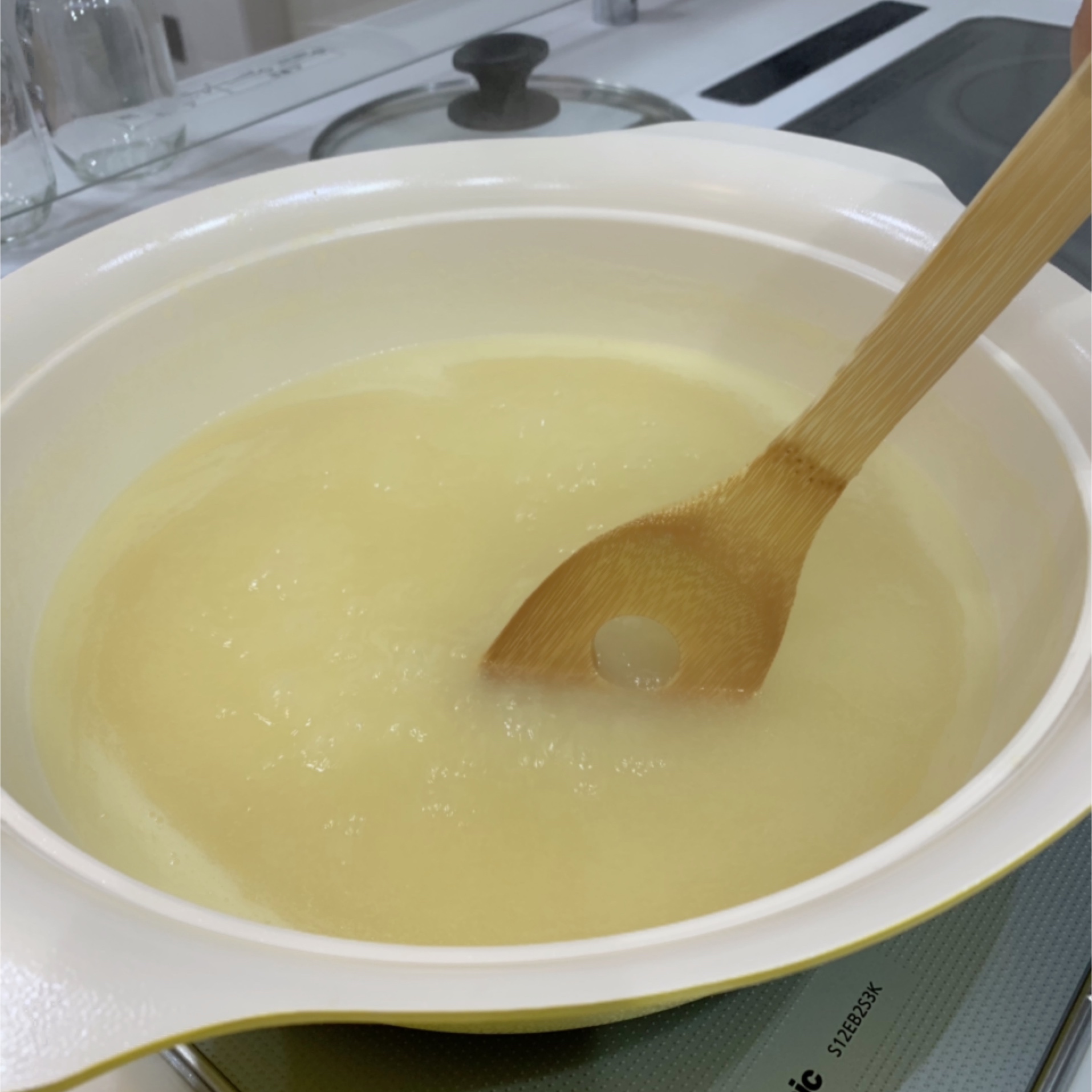



見た目通りに、とっても美味しいジャムが出来ました♡♡♡
また、来年も一緒に作りたいです(ˊᗜˋ)