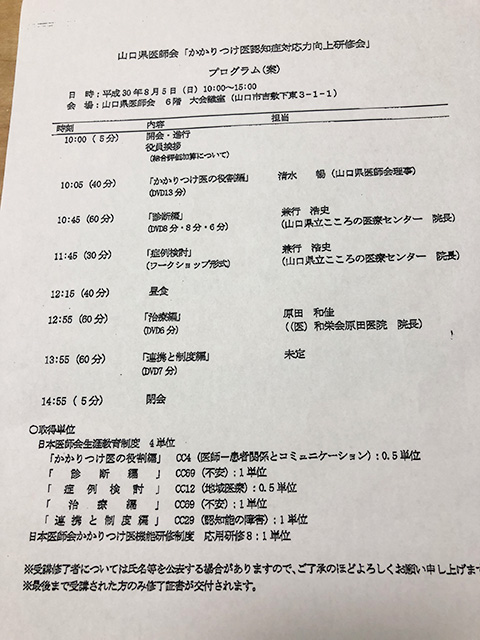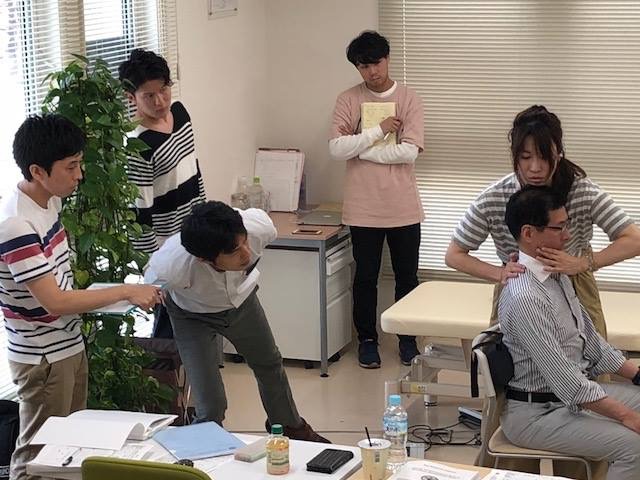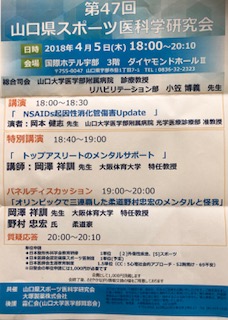日医かかりつけ医機能研修制度に参加しました〜その2
2018/05/31
午後から飯島先生のフレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)がありました。フレイルとは心身機能の顕著な低下を虚弱と呼ばれ要介護状態への最たる要因です。健康な状態と要介護状態の中間地点で、しかるべき適切な介入により機能を戻すことができる(可逆性)、身体の虚弱だけでなく認知の虚弱、社会性の虚弱が存在することから多面的であります。フレイルの評価方法としてJ-CHS基準があり、半年で2-3kgの体重減少、握力の低下(男性26kg未満、女性18kg未満)、二週間でわけもなく疲れる疲労感、1m/s未満の歩行速度、身体活動していないのうち3項目を満たすという方法があります。BMIパラドックスという言葉がありやせの方が総死亡率が高い、糖尿病患者で厳格な管理を行ってもフレイルのリスクが高くなることなどが挙げられますので、年齢別にカロリー摂取に関する考え方のギアチェンジを行う必要があるとのことでした。一方サルコペニアは筋肉減少症で筋肉量の減少を必須として筋力低下又は身体能力低下のいずれかがあればサルコペニアと診断する報告もあります。サルコペニアの画像診断では全身のDEXA法、バイオインピーダンス法があります。高齢者の骨格筋には蛋白同化抵抗性という現象があり、より多くのアミノ酸摂取が必要になるそうです。ふくらはぎを親指人差し指で掴めるか否かの指輪っかテストは総死亡率が差があるそうです。又残歯が20本未満、噛む力が弱い、舌の力が弱い、滑舌が悪い、固い食品が食べにくい、むせが増えたのうち3項目以上をオーラルフレイルと診断され、口腔ケアの衰えがフレイルの原因になるので栄養、身体活動、社会参加は健康長寿及びフレイル予防を実現する柱になるそうです。サルコペニア対策としてのリハビリテーション栄養として筋肉のエネルギーであるBCAA:分岐アミノ酸が重要です。
高齢者総合的機能評価(CGA)とは疾患評価以外の生命予後と機能予後を改善する為の評価手技で、健康寿命の延伸を実現する為にはフレイル、オーラルフレイル対策が急務とのことです。
津田先生のかかりつけ医の栄養指導を拝聴しました。日本人の平均寿命と健康寿命は男性で9年、女性は12年の開きがあ、健康寿命の延伸が課題です。個人レベルのみでなく、社会レベルでの対策が必要でその中で栄養、食生活の目標設定、身体活動の目標設定、休養の目標設定をされています。食事バランスガイドがあり、主食、副菜、主菜の順に書いてあります。栄養療法には経口、経腸、経静脈栄養がありますが中心静脈栄養は減少傾向にあります。医療機関では多職種で栄養サポートチームの介入を行うことが望ましいです。栄養治療はアセスメントとして主観的評価のSGA、簡易栄養状態評価法としてのMNA-SFなどがあり、客観的評価と合わせて治療計画、実施、再評価を行います。過栄養になると生活習慣病、低栄養になると老年症候群になりやすいので栄養介入を行います。食事指導のポイントは腹八分目、種類は多く、脂肪控えめ、食物繊維を多く含む野菜、海藻、きのこなどをとり、三食規則正しく、ゆっくり噛んで食べることです。栄養素の特性からみた優先順位としてエネルギー、栄養素では蛋白質、脂質、ビタミンA,B,C,Ca,Feの順に食べます。エネルギー管理の基本は毎日体重を計ることが重要です。推定エネルギー必要量は基礎代謝量×身体活動量で基礎代謝量は推定式を使用します。筋肉の役割として運動器の機能に加えて、熱源(基礎代謝)、循環の補助、骨体の保護、マイオカイン分泌(情報伝達物質)があり、運動と栄養の併用が重要であるとのことでした。
最後に和田先生と木村先生のかかりつけ医の在宅医療、緩和医療を拝聴しました。地域包括ケアシステムは2012から導入されました。医療、介護、住まい、予防、生活支援を日常生活圏で提供し、住みなれた地域で最期まで暮らせるシステムを治療にあった形で構築するシステムです。在宅医療・介護連携推進事業は2018年から市町村レベルでの地域包括ケア具現化の為の政策の一つです。又介護予防・日常生活支援総合事業とは2017年度から全ての市町村で行われている要支援、要支援になる可能性のある65才以上の人を対象に介護予防訪問看護と介護予防通所介護を総合事業に移行させるものです。多職種連携によるケアマネジャーとの連携、サービス担当者会議、地域ケア会議、病診連携による退院前カンファレンス、在宅診療、訪問診療、居住系施設での在宅医療などを解説して頂きました。急性期ケアとして在宅医療での身体診察と検査、褥瘡のチェック、大腿骨近位部骨折の診断、在宅医療での治療としての気管切開の管理、中心静脈栄養の管理、膀胱カテーテル管理、入院の判断のチェックなども教えて頂きました。慢性期ケアとして身体診察、栄養アセスメント、総合的機能評価、摂食嚥下障害、認知症、排便排尿障害、慢性呼吸不全、慢性心不全などについてベースラインの身体情報を把握することの重要性などを教えて頂きました。在宅緩和ケアは悪性腫瘍だけでなく、疼痛はtotal painとして考え、本人や家族への意思決定を尊重し、多職種で看取りを念頭においたケアを提供することが肝要です。家族に対するケアも必要でありうつの診断も必要とされます。ガン患者への緩和ケアはガン疼痛の評価、オピオイドの適切な治療、悪心嘔吐対策、せん妄、抑うつ、不眠に対するケアも必要となります。非ガン患者への緩和ケアでは脳血管障害、肝不全、腎不全、呼吸不全、心不全、認知症の終末期医療も対象になります。最近ではアドバンス・ケア・プランニングという患者の意思決定を支援する活動が注目されていることも教えて頂きました。
最後に症例検討があり終了しました。
高齢者総合的機能評価(CGA)とは疾患評価以外の生命予後と機能予後を改善する為の評価手技で、健康寿命の延伸を実現する為にはフレイル、オーラルフレイル対策が急務とのことです。
津田先生のかかりつけ医の栄養指導を拝聴しました。日本人の平均寿命と健康寿命は男性で9年、女性は12年の開きがあ、健康寿命の延伸が課題です。個人レベルのみでなく、社会レベルでの対策が必要でその中で栄養、食生活の目標設定、身体活動の目標設定、休養の目標設定をされています。食事バランスガイドがあり、主食、副菜、主菜の順に書いてあります。栄養療法には経口、経腸、経静脈栄養がありますが中心静脈栄養は減少傾向にあります。医療機関では多職種で栄養サポートチームの介入を行うことが望ましいです。栄養治療はアセスメントとして主観的評価のSGA、簡易栄養状態評価法としてのMNA-SFなどがあり、客観的評価と合わせて治療計画、実施、再評価を行います。過栄養になると生活習慣病、低栄養になると老年症候群になりやすいので栄養介入を行います。食事指導のポイントは腹八分目、種類は多く、脂肪控えめ、食物繊維を多く含む野菜、海藻、きのこなどをとり、三食規則正しく、ゆっくり噛んで食べることです。栄養素の特性からみた優先順位としてエネルギー、栄養素では蛋白質、脂質、ビタミンA,B,C,Ca,Feの順に食べます。エネルギー管理の基本は毎日体重を計ることが重要です。推定エネルギー必要量は基礎代謝量×身体活動量で基礎代謝量は推定式を使用します。筋肉の役割として運動器の機能に加えて、熱源(基礎代謝)、循環の補助、骨体の保護、マイオカイン分泌(情報伝達物質)があり、運動と栄養の併用が重要であるとのことでした。
最後に和田先生と木村先生のかかりつけ医の在宅医療、緩和医療を拝聴しました。地域包括ケアシステムは2012から導入されました。医療、介護、住まい、予防、生活支援を日常生活圏で提供し、住みなれた地域で最期まで暮らせるシステムを治療にあった形で構築するシステムです。在宅医療・介護連携推進事業は2018年から市町村レベルでの地域包括ケア具現化の為の政策の一つです。又介護予防・日常生活支援総合事業とは2017年度から全ての市町村で行われている要支援、要支援になる可能性のある65才以上の人を対象に介護予防訪問看護と介護予防通所介護を総合事業に移行させるものです。多職種連携によるケアマネジャーとの連携、サービス担当者会議、地域ケア会議、病診連携による退院前カンファレンス、在宅診療、訪問診療、居住系施設での在宅医療などを解説して頂きました。急性期ケアとして在宅医療での身体診察と検査、褥瘡のチェック、大腿骨近位部骨折の診断、在宅医療での治療としての気管切開の管理、中心静脈栄養の管理、膀胱カテーテル管理、入院の判断のチェックなども教えて頂きました。慢性期ケアとして身体診察、栄養アセスメント、総合的機能評価、摂食嚥下障害、認知症、排便排尿障害、慢性呼吸不全、慢性心不全などについてベースラインの身体情報を把握することの重要性などを教えて頂きました。在宅緩和ケアは悪性腫瘍だけでなく、疼痛はtotal painとして考え、本人や家族への意思決定を尊重し、多職種で看取りを念頭においたケアを提供することが肝要です。家族に対するケアも必要でありうつの診断も必要とされます。ガン患者への緩和ケアはガン疼痛の評価、オピオイドの適切な治療、悪心嘔吐対策、せん妄、抑うつ、不眠に対するケアも必要となります。非ガン患者への緩和ケアでは脳血管障害、肝不全、腎不全、呼吸不全、心不全、認知症の終末期医療も対象になります。最近ではアドバンス・ケア・プランニングという患者の意思決定を支援する活動が注目されていることも教えて頂きました。
最後に症例検討があり終了しました。