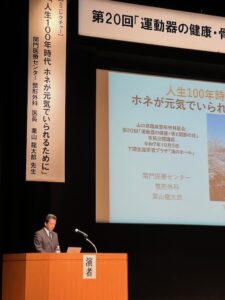10/5下関生涯学習プラザで第20回運動器の健康・骨と関節の日記念行事があり参加しました。毎年臨床整形外科医会が各地区持ち回りで講演会を行なっています。ロコモ体操、開業医の先生の一問一答の後に関門医療センター整形外科栗山部長の「人生100年時代ホネが元気でいられるために」を拝聴しました。介護の原因として運動器の障害が25%を占めています。加齢と共に骨量が減少し骨粗鬆症になります。骨は身体を支える支持機能、内臓を守る保護機能、血液を作る造血機能、カルシウムを蓄える貯蔵機能などがあります。骨粗鬆症では骨吸収が骨形成を上回り骨折しやすくなった状態で食事、運動、薬物、手術療法がありそれぞれ紹介されました。
次いで山口大学整形外科坂井教授の「しっちょる?ロコモ やっちょる?ロコモ対策」を拝聴しました。ロコモ(ロコモティブシンドローム)とは運動器の障害で移動機能の低下をきたした状態で要支援、要介護の原因になります。骨粗鬆症(推定1280万人)、変形性膝関節症(2530万人)・変形性腰椎症(3790万人)、サルコペニア(筋肉減少症850万人)、腰部脊柱管狭窄症(500万人)などの疾患があり、それぞれわかりやすく解説して頂きました。運動習慣のない生活、痩せすぎ・肥満なども原因となります。ロコチェックとして片足立ちで靴下がはけない、など紹介されロコモの判定で片足で40cmの高さから座って立ち上がり可能か?2ステップテストなどでロコモ度を判定します。ロコモの解決策としてロコトレがあり片足立ち、スクワットに加えてボックスステップを紹介されました。